環境学と私
このコーナーでは、環境学研究科の教員や修了生がそれぞれの関心や出来事について広く語りかけます。
ダム撤去の政策過程
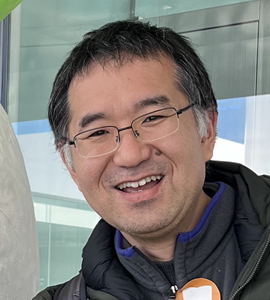
社会環境学専攻 環境法政論講座
大野 智彦 准教授
本教員のプロフィール
2025年4月に環境法政論講座に着任しました。私自身が博士(地球環境学)という学位をいただき研究者としての歩みを始めたので、環境学の大学院で仕事ができることをとても嬉しく思っています。
私が関心を持っているのは、環境問題についての社会的な意思決定の仕組みです。自然環境は様々な人や組織に影響を与えますが、それゆえに、どのような環境が望ましいのかについて合意することが難しい状況も多々あります。そうしたなかで、どのような意思決定の仕組みが望ましいのかを考えたいと思っています。とはいえ、現実の意思決定の経緯は非常に複雑ですから、まずは過去の意思決定がどのように行われたのか、政策過程論のフレームワークや手法を使って明らかにする作業を続けています。そのような作業を積み重ねることで、どのような意思決定の仕組みが望ましいのかという問いへの答えが見えてくればと思っています。
具体的な対象としては、川や水に関する問題に関心を持ってきました。例えば、ダムを建設するかしないかといった問題がどのように意思決定されてきたかについて、資料を調査したり、関係者の方にインタビューをさせていただいたりしながら調べてきました。
最近特に関心を持っているのは、ダム撤去の政策過程です。老朽化や、地域社会・環境への悪影響を背景として、ダムが撤去される事例がアメリカやヨーロッパで増えつつあります。日本でも熊本県球磨川の荒瀬ダムが、2018年に撤去されました。1955年に建設された同ダムは発電専用ダムとして戦後の電力不足解消に貢献しましたが、同時に周辺地域に様々な悪影響を及ぼしていたことから、立地自治体から撤去の要望が上がり、紆余曲折を経て撤去されることになりました。
ダムを建設するかしないかという議論を追いかけていた私にとって、現存するダムが撤去されたことは大きな衝撃でした。そして、そのような大きな変化のプロセスを研究することは、いま様々な環境問題において求められている社会変革を可能にする道筋を見いだすことにつながるのではないかと思っています。


(オオノ トモヒコ)

